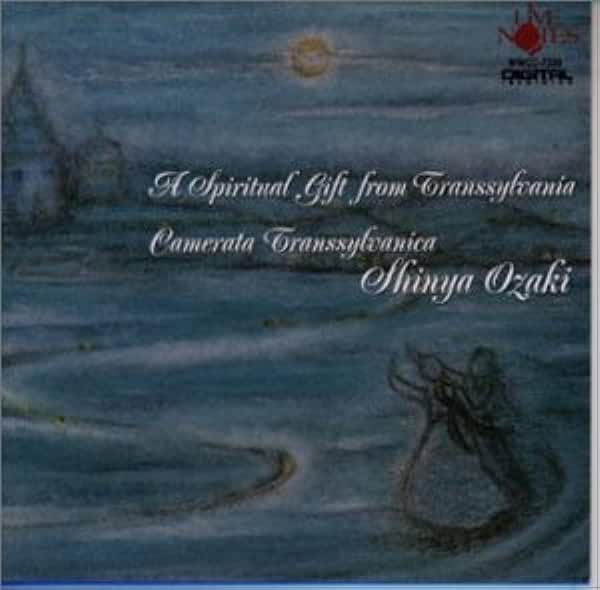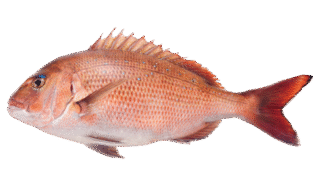「M.M.=120」。楽譜には、曲の頭にこういう記号が書いてあることがある。速度に関しての作曲家の指定だ。「メルツェル・メトロノーム」の略で、ヨハン・ネポムク・メルツェルという人が特許をとったメトロノームという意味。ギリシャ語でメトロは「測定する」、ノームは「方法」。つまり機械による測度記号なのだ。M.M.の意味を知らない音楽家が多い。「メトロノームマーク」なんて思っている人、勉強不足です。反省しなさい!

楽曲に初めてメトロノームを使った音楽家はベートーヴェンだ。メルツェルはウィーンにいて、ベートーヴェンと交流があったのだ。よく知られているように、ベートーヴェンは難聴だった。そんな彼のために発明家メルツェルは補聴器も作っている。補聴器といっても現在のように小さいものではなく、医者の使う聴診器を巨大にしたようなもの。見た目は悪い。プライドが高いベートーヴェンはどのような気持ちで使っていたのだろうか。

ベートーヴェンは補聴器のお礼に、「タ、タ、タ…親愛なるメルツェルよ、ごきげんよう」という曲を作っている。彼の最も短い楽曲の一つだ。彼はメトロノームを使って、今まで作った作品に測度記号を書き込んでいった。メトロノームの音が聞こえない彼には、針が振り子のように左右に動いて、テンポを視覚的に捉(とら)えることができるメルツェル式メトロノームはさぞかし強い味方となっただろう。振り子が動いているのを見ながら、「えーと、このメヌエットは一拍が一分間に120くらいの速さかなあ」なんてやっていたのだろうか。
さて、メトロノームが無かった時代は、どうやって速度を決めていたのだろうか。答えは「脈拍を使っていた」である。音楽家で知らなかった人、また反省しなさい! 十八世紀の音楽教本などには、「この場合のアレグロは一拍が脈拍の二倍の速さ」といった記述がある。演奏会の前にアドレナリンが出て脈拍速度が上がっていった場合はどうなるんだろうか。

近年空港のセキュリティーチェックが厳しい。荷物検査場で荷物を開けさせられる事も珍しくなくなった。一度、ミュンヒェン空港の荷物検査場で荷物を開けた時に電子音が鳴りだしたことがある。「ピッ、ピッ、ピッ、…」。職業柄即座に「テンポ60だな」。そう、荷物の中の電子メトロノームのスイッチが入ってしまったのだ。小さな名刺大の機械はテンポ60、つまり時計の秒針と全く同じ速さを電子音で刻んでいた。それはスパイ映画にでてくる時限爆弾みたいな音だった。気づけば厳しい顔の係官に囲まれている。「あれれれ、これ、メトロノームですから、なんで鳴ったんですかね。おかしいな」と意識的に笑顔を作って説明した。即刻拘束後別室移動事情聴取! なんてまっぴらだもの。不自然な笑い顔で後ろを向くと、まわりには不気味な静寂があり、乗客の凍り付いた表情がそこにあった。まったく物騒な世の中になったものだ。

2007/12/09
追記
このエッセイを書いた当時はカード上の電子の小さいメトロノームを使っていました。
今はスマートフォンにメトロノームのアプリを入れて測定しています。時代は変わりましたね。
エッセイについて
これは南日本新聞に11年間150回にわたり連載した「指揮棒の休憩」というエッセイです。長く鹿児島の読者に読んでいただいて感謝しています。今回、このブログにも掲載します。

\エッセイをまとめた本・好評です!/
\珍しい曲をたくさん収録しています/
\ショパンの愛弟子・天才少年作曲家の作品集・僕の校訂です!/
\レコーディング・プロデューサーをつとめて制作しました!/