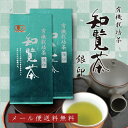鹿児島県「荒茶」生産量日本一
2024年の「荒茶」の生産量で、鹿児島県が全国1位になりました! 65年間連続トップであった静岡県を抜いたのです。これは、調べてみると、1959年調査開始以来だそうです。1959年といえば、僕の生まれた年です。長く、荒茶生産高のトップは静岡県だったのですね。

<以前投稿したものです/鹿児島のお茶生産の歴史等書いてあります>


荒茶とは
荒茶とは、茶畑でとれたままのお茶のことです。
しかし、とれたままのお茶は葉は、そのままでは酸化がすすんでしまいます。お茶の香りも鮮やかな緑色も失われてしまうのです。
そのために、収穫した生葉はお茶農家が生葉を茶畑から製茶工場に運び、蒸して揉んで乾燥させます。そうして、茶葉の酸化をとめるのです。

一般的に、できあがった荒茶(あらちゃ)は、市場などを通じてお茶問屋さんのもとへ運ばれます。そして、問屋さんで荒茶(あらちゃ)は、二次加工されます。それは、茶葉の大きさをそろえるためにきざまれたり、ほかの産地の茶葉と合組(ごうぐみ→ブレンド)されたりするのです。
こういう過程で作られたお茶が私たちのもとに届けられるわけです。

鹿児島茶の生産

最大の栽培地域は南九州市から枕崎市にかけて広がる南薩台地付近であり、県内における茶栽培面積の約40パーセントを占める。そのほか鹿児島市付近の中薩台地、さつま町から霧島市にかけての北薩火山群および霧島山の山裾、志布志市から曽於市にかけての鰐塚山地南西部が主要栽培地域である。
茶畑は大規模化と機械化が進んでおり、平成18年(2006年)における栽培面積は8460ヘクタール、鹿児島県内ではイネ、サツマイモに次ぐ栽培面積を有する。荒茶生産量は23000トンで日本の25.4パーセントを占めているが、大部分は仕上げ加工において他産地の茶にブレンドされ他産地のブランド名を冠して市販される。
このような中にあっても、特に知覧茶と霧島茶は独自のブランドとして認知されている。