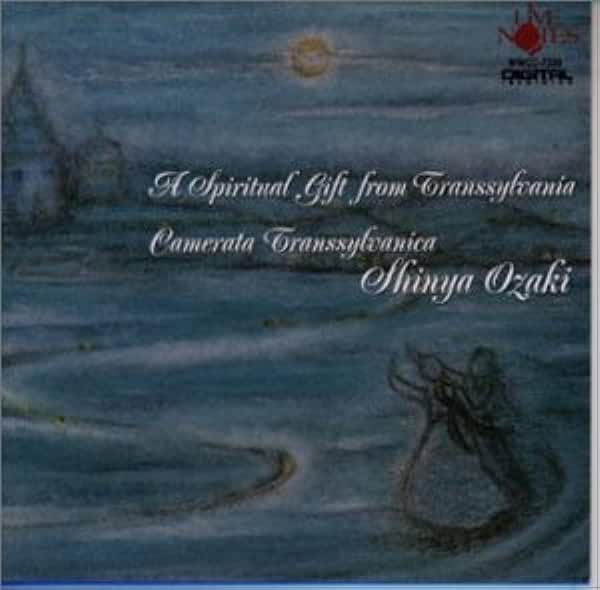午後九時半。文化宮殿の重たい鉄の扉を押し開き、夜の濃い霧の中へ足を踏み出す。この中世風の装飾のある厳かな扉は外界との境界。その威容が宮殿に足を踏み入れる者を気高き芸術の前にひれ伏せさせる。
外は零下五度、注意して石の階段を下りる。今夜のソリスト、アレックスと歩く。彼はスイスに住んではいるが、ルーマニア出身のヴァイオリニストだ。プログラムの二曲目のヒンデミットのヴァイオリン協奏曲を一緒に演奏した。二十世紀のモダンな曲で、あまり知られていない。僕も初めての指揮で勉強が大変だったが、彼もオーケストラも、皆初めて挑戦する曲だった。一回の練習、それもたった二時間で仕上げなければならなかったが、本番はとてもうまくいった。

二人とも足元に注意しながら歩いていたので言葉は少なくなる。レストランでの温かい食事は寒さで冷えきった体に染み入るようだった。アレックスとは昨日の練習と本番にしか会っていないので、初対面も同然だった。彼とは英語で話していたが、話が進むにつれ、ルーマニア語に切り替えた。お互いの紹介や生活など話は弾み、メインディッシュを食べるころには気心がしれた関係になっていた。演奏と同じく、とても繊細な人間だった。
「ところでアレックス、なんでスイスに住んでいるの」。何気なく単純な質問をぶつけた。「僕は難民だったんだよ」。「リフジー(難民)」という言葉に耳を疑った。「七七年にチャウセスク政権から政治難民としてスイスに逃げたんだよ。コンクールのためにスイスに行ったのが二十七歳の時。そのままスイスにとどまり、もう祖国には帰らないって宣言したんだ」

アメリカに住んでいるときに、ベトナムからの難民で移民してきた知り合いがいたが、音楽家では初めてだ。そういえばヒンデミットはドイツ人だが、ナチスに「頽廃(たいはい)芸術」と烙印(らくいん)を押され、作品上演を禁止された。そして彼も弾圧から逃れるためスイスに亡命したのだ。ワーグナーやストラヴィンスキーをはじめ、政治的理由でスイスに亡命した音楽家は数限りない。スイスは人道主義的な立場から長年難民を受け入れ続けてきた。今でも国民の三分の一近くは国外からの移住者とその子孫である。「両親はブラヴォーって、僕が国外にとどまるのを祝ったよ」。もの静かにほほ笑む彼だが、本当のところはお互いに複雑な気持ちだったに違いない。八九年の革命の後、解放され二十年近くたったルーマニアは、彼の目にはどう映るだろうか。
デザートとコーヒーが終わり、帰ろうとするころ、彼は思い出したように言った。「僕らの仕事って本当に感謝の多い仕事だよね。こんなに勉強して、そしていい体験をしてお金をもらうこと自体、恵まれていると思わない? このお金はギャラじゃないよ。僕らへの奨学金なんだ」

ファンシーなレストランの扉は回転ドアだった。子供が回したドアから、僕らは外へ出た。子供たちの笑い声が高い空に響く。ルーマニア独特の霧は、もう晴れていた。
2008/03/09
エッセイについて
これは南日本新聞に11年間150回にわたり連載した「指揮棒の休憩」というエッセイです。長く鹿児島の読者に読んでいただいて感謝しています。今回、このブログにも掲載します。

\エッセイをまとめた本・好評です!/
\珍しい曲をたくさん収録しています/
\ショパンの愛弟子・天才少年作曲家の作品集・僕の校訂です!/
\レコーディング・プロデューサーをつとめて制作しました!/