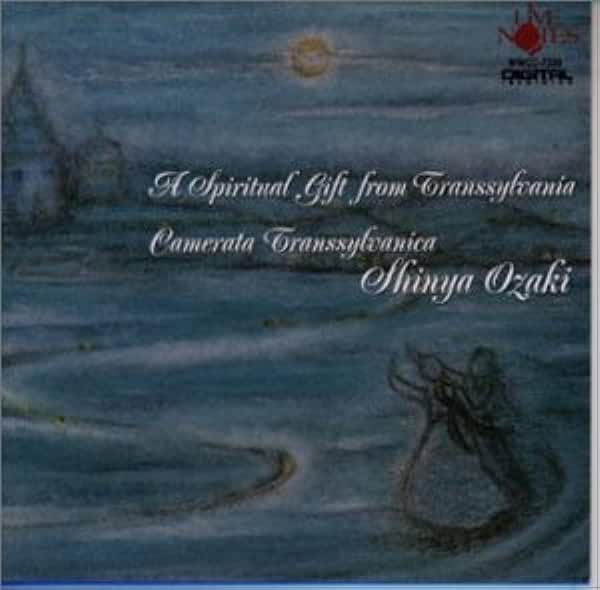宇治川の畔(ほとり)。豊富な水の流れを眺めながら歩くと、脇に平等院が見える。
 SONY DSC
SONY DSC「水の流れと人の末」。一〇五二年、末法元年とされるこの年、宇治大将と呼ばれた藤原頼通が譲り受けた地を仏寺に改めた。まさしく水の流れのように行く先不安な時に、頼通が極楽往生を切なる願いに、極楽浄土を再現したのだ。その代表的な建築物、鳳凰堂は、直接的にも間接的にも日本人なら見たことのない人はいないだろう。十円硬貨の表には鳳凰堂が、一万円札には屋根の上の鳳凰がデザインされているんだもの。(余談ですが、コインの表は絵柄のある方です)

日本滞在中はなるべく日本文化に触れることができるところを訪れることにしている。京都はよく足を運ぶ地だが、最近は欲を張らず、一回の訪問で一つの寺院だけを訪れる。かつて限られた時間に駆け足で回った寺院の一つ、平等院もゆっくりと回れば、また違った感想を持つ。
鳳凰堂も美しいが、内部の本尊を囲む「雲中供養菩薩像」は音楽家の僕にはとりわけ興味深い。五十二体の菩薩が雲に乗り、楽器を奏で、歌い、そして踊っているのだ。これらの像は定朝という仏師の工房で作られたもので、数ある静の仏像に対して、動。対極にある。従来の仏像の形式の枠を外れた表現に、自由な思いが感じられる。仏師が喜々として作ったものに違いない。生き生きとしたその表情は千年前のテクニックだけではなく、仏師の思いも伝える。かつて頼通は、ここで一人静寂の中心の耳を澄まし、西方浄土の幸せに満ちたにぎやかな音楽を聞いていたのだろう。
楽器類は弦楽器、管楽器、打楽器とさまざまだが、数からすると打楽器が多い。天上に響く音楽はたいへん華やかな音楽なのだろう。それに舞が加わり、金色のお堂の中はまるでダンスホールだ。壁画の色も当時は極彩色だった。
この中でも面白いのは「拍板(はくはん)」と説明される楽器を持った像。「南23号像」と素っ気ない名なのだが、「平等院には手風琴をもった仏像がある」と、昔のアコーディオン雑誌に載っていたという。手風琴とはアコーディオンのこと。確かに蛇腹を持った楽器にも見えたのだろう。全国のアコーディオン愛好家にもぜひ見てほしいものだ。しかし、手風琴を作る技術は比較的新しいものだから、これは木片をつないだ打楽器「拍板」だという説を僕は採る。

お堂の中のゆっくり流れる時間を断ち切り、出口に向かう。門を出た所で、ふと思った。「あれ、指揮者がいないな」。すぐに仏教に詳しい弟子にメールを送った。「極楽浄土には指揮者いないのかな。もしかしたら中央の阿弥陀如来が指揮者かね」。すぐに弟子から返事がきた。「あれも雅楽と一緒で、日本の音楽に指揮者はいないんじゃないでしょうか。尾崎先生、阿弥陀如来になっちゃだめですよ。衆生を救いにあっちこっち駆けずり回る羽目になりますよ」
2008/01/13
エッセイについて
これは南日本新聞に11年間150回にわたり連載した「指揮棒の休憩」というエッセイです。長く鹿児島の読者に読んでいただいて感謝しています。今回、このブログにも掲載します。

\エッセイをまとめた本・好評です!/
\珍しい曲をたくさん収録しています/
\ショパンの愛弟子・天才少年作曲家の作品集・僕の校訂です!/
\レコーディング・プロデューサーをつとめて制作しました!/